6章 この国のかたち 世界からみると




先進国の多くは、医療や年金、介護などで社会保険方式をとっていますが、社会保険料の本人負担と事業主負担はどうなっているのでしょうか。勤労者の年収に占める保険料率を、本人負担分と事業主負担分にわけて、国際比較してみましょう。
給与から天引きされる本人負担は、スウェーデン7.0%、フランス9.6%、ドイツ21.0%、日本10.9%となっています。一方、事業主負担分は、スウェーデン28.6%、フランス32.0%、ドイツ21.0%などと日本の11.3%と日本を大きく上回っています。

金融広報中央委員会の発表によると、金融資産保有額は85年から伸びており、先進5ヵ国の中でアメリカに次いで第2位となっています。反面、無貯蓄世帯が2割強となっています。金融資産の保有額が増えながらも、無貯蓄世帯が増加するという状況になっています。



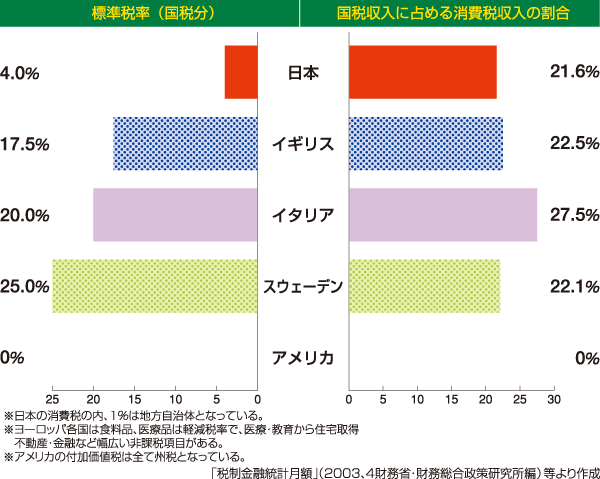

「日本の消費税率5%は、国際的にみれば低すぎる」「福祉先進国のスウェーデンの5分の1、欧州各国の4分の1」とよくいわれます。しかし、国税収入に占める消費税収入の割合をみると、約22%と、まったく同程度であることがわかります。
これは、日本の消費税が「網羅的」に課税されているのに対し、欧州各国の付加価値税は、①医療・教育から住宅取得・不動産・金融など幅広い非課税項目があること、②食料品や医薬品など、生活必需品は軽減税率をとっているためです。
財界は、消費税率を10%から18%に引き上げることを要求しています。そのねらいは、企業の税・社会保障負担を軽減することです。企業負担の軽減分は、国民が負担することになります。
政府や与党のなかには、「社会保障の財源充実のために消費税増税を」という動きがあります。これ以上、消費税率を引き上げれば、国際的にみても「異常な国」となることは明らかです。





消費税は、低所得者ほど負担が重い「逆累進性」の性格をもつ税金で、導入から15年がたちました。消費税が導入されて以降10数年で、国税収入に占める消費税の割合は、7%から22%に上がっています。一方、法人税は36%から22%に、所得税は37%から34%に下がっています。これは、企業減税や高所得者減税、長引く不況によるものです。



政府は、日本の法人税は高すぎると、連続して法人税減税を行なってきました。1988年には42%だった税率が、2003年には30%に下がっています。15年間の消費税の税収は136兆円にのぼりますが、同じ時期の大企業から税収(法人3税)は131兆円も減収しており、消費税が大企業の納めるべき法人税の減税・減収の穴埋めにされています。
日本の直接税と間接税の比率は、1990年度に70%対30%だったものが、2000年度には60%対40%に、そして2002年度には56%対44%になっています。
 |
|