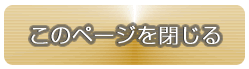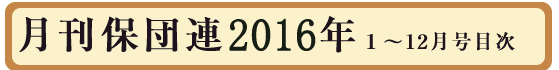

─より良く食べるはより良く生きる─
●高齢者の増加に伴い、今後ますます医療・介護の需要は高まっていくことが予想される。その中で近年「口から食べる」ことの重要性が広く認識されはじめている。
●口腔が健康の増進、保持、回復、療養に果たす役割はとても大きい。また口腔ケアが肺炎予防に果たす役割、咬合が嚥下に果たす役割も注目されている。
●「口から食べる」ことが多くの役割を果たし、貢献していることはもとより、人間の尊厳を守ることであることも忘れてはならない。
─ロコモ・サルコペニア─
●ロコモとサルコペニアはともに高齢期の身体機能低下ひいては要介護化の予防を目指した概念である。
●ロコモは運動器の障害により移動機能の低下した状態であり、日本整形外科学会から提唱され、3つのロコモ度テストで程度が判定される。
●サルコペニアは欧米の老年医学の分野から提唱され、筋量の低下をベースとして、筋力(握力)、身体機能(歩行速度)の3つから、アジアの基準値にて判定される。
●包含関係でいえば、サルコペニアはロコモに含まれるが、両者の視点は異なり、サルコペニアでは筋肉を全身的状態との関連でとらえている。対策は運動と栄養指導を両者合わせて行い、継続することが大切である。
●フレイルの中核要因は、低栄養とサルコペニアである。
●廃用症候群では、サルコペニアのすべての原因(加齢、活動、栄養、疾患)を認めることが多い。
●活動と栄養によるサルコペニアは、急性期病院で医原性サルコペニアとして作られることがある。
●サルコペニアの対応は原因によって異なり、リハビリテーション栄養の考え方が有用である。
●ここでフレイルティの定義(Freid)において、有害事象の予測因子には優先順位であり、歩行速度>握力>体重減少が重要であることを認識する必要がある。
─在宅NST(栄養サポートチーム)の試み─
ドロップアウトした患者には何の救いにもならない可能性がある。
●「口から食べられない」ハンディキャップを抱えた患者に対峙する際、「どんなあなたでも支える」という心構えが必要である。例えば、「胃ろうを否定しない」ことが最も分かりやすい。「口から食べさせたい」の対極にある「憎き」胃ろうを認めることが、なぜこのテーマの解決策になるのかを在宅NST(nutrition support team、栄養サポートチーム) の取り組みを通して理解いただきたい。
─大気汚染対策の陰でつづく被害者の放置─
◆今なお症状のコントロールが利かず、「受診抑制」や薬の「節約」などをして病気と生活破壊の悪循環に陥る患者が少なからず存在する。
◆東京都の救済制度も風前のともしびとなり、国が制度創設に乗り出さねば結果的に社会的費用を増大させることになる。
─沖縄基地・TPP など諸問題を例に─
●訪問現場でみられる咀嚼の問題を考えたときに、自宅療養を余儀なくされている原因である身体機能障害を考慮する必要があります。身体機能障害のもとになる運動障害は咀嚼障害の原因となるからです。これらの対応とは、運動の要素を考慮した機能低下に内容に応じた運動訓練の提示と、病態を理解した対応となります。原因疾患によっては、回復は不能である場合も多く、咀嚼機能の改善は見込めません。その際には、安全でおいしく食事ができる方法を提案しなければなりません。