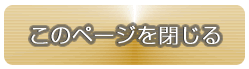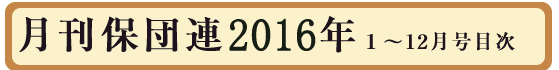
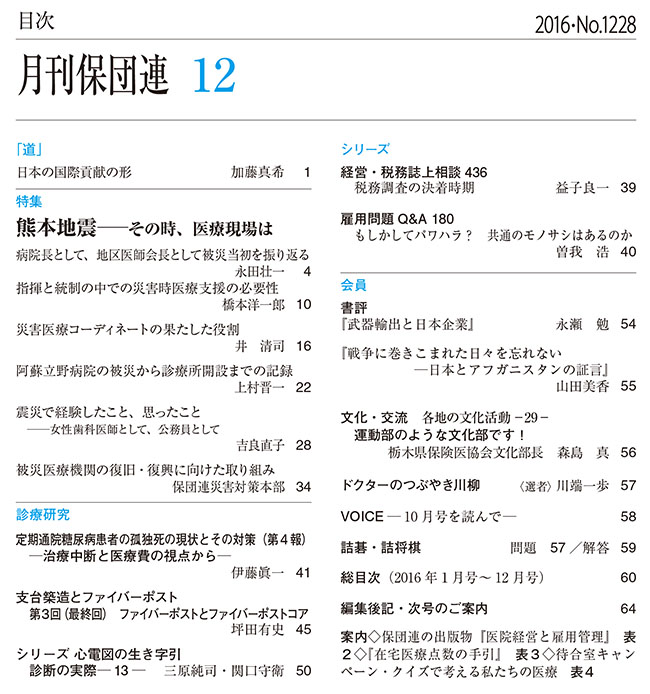
2016・No.1228
月刊保団連 12
PDF内の写真・文章の無断転載を固く禁じます。
「道」
日本の国際貢献の形
特集
熊本地震─その時、医療現場は
病院長として、地区医師会長として被災当初を振り返る
●2016年4月14日、16日の2回、誰もが経験したことのない震度7を立て続けに経験した。しかも、東熊本病院の入院患者達の広域搬送中に本震が発生した。その状況下、多くのDMATチーム、救急隊のおかげで、人的被害を出さずに搬送完了できたことは奇跡に近い。
一方、被災した医療機関が災害医療に取り組むことは多くの困難が生じるが、今回、災害医療調整本部長とし
て被災者支援も経験した。両方の立場を経験したことは、今後の災害医療を考える上で貴重な体験であった。
指揮と統制の中での災害時医療支援の必要性
●熊本地震において4月19日より開始された深部静脈血栓症(DVT)検診は、当院を中心とした熊本のメンバーが受け皿となって、多くのボランティアの方々と一緒に行った。4月21日に県庁で「日本循環器学会専門チーム『エコノミークラス症候群』予防活動に関する打ち合わせ」が開催され、熊本大学循環器内科を中心に熊本地震血栓塞栓症予防(KEEP)プロジェクトが始動し、着実な効果を示していった。災害時にはcommand and control(指揮と統制)の中での医療支援の必要性を実感した。
災害医療コーディネートの果たした役割
●熊本県は災害医療コーディネート研修会を開催し、県内の医師会、保健所長、県庁担当部局職員などが参加し、活動や役割について関係者のイメージの共有化を図っていた。
●4月14日の発災以降、登録された医師は交代で勤務にあたり、県庁の医療調整本部の下に二次医療圏毎に保健所長や医師会長などを中心とする医療調整本部を設置し、救護班の活動の調整を行い、情報交換の会議を開催した。
●指揮系統が大きな混乱なく運営できたのは、事前準備と取り決め、発災直後の全体集会での方針確認が大きかった。
●4月14日の発災以降、登録された医師は交代で勤務にあたり、県庁の医療調整本部の下に二次医療圏毎に保健所長や医師会長などを中心とする医療調整本部を設置し、救護班の活動の調整を行い、情報交換の会議を開催した。
●指揮系統が大きな混乱なく運営できたのは、事前準備と取り決め、発災直後の全体集会での方針確認が大きかった。
阿蘇立野病院の被災から診療所開設までの記録
●熊本地震から6カ月が経過した。「諸行無常」─古昔より災害国であるわが国の代表的な観念である。論ずるまでもなく、われわれ医師は、患者に対する義務、職業に対する義務、公衆衛生に対する義務を負っている。今回の地震は医師としての義務、使命はもとより、経営者としての責任をいやというほど認識せざるを得なかった。ここでは本震後最初の3日間、4日目から1カ月、そして1カ月以降を可及的に時系列にして記した。
震災で経験したこと、思ったこと
─女性歯科医師として、公務員として
●行政に勤める歯科医師として、避難所の運営に関わった。被災者の健康課題は、発災前からの課題が顕在化したものも多かった。ニーズ把握は被災者に寄り添って、信頼を得て行うべきだと思う。現場では誤嚥性肺炎の予防等の情報も提供したが、効果は不明。被災者は唾液の減少が顕著で、口臭、食欲減退等、QOLとの関連が推測された。唾液の減少対策も必要。避難所の性暴力については、認識に男女差・個人差が大きく、セカンドレイプの問題は小さくない。今後の研修と意識の向上が必要だと思う。
被災医療機関の復旧・復興に向けた取り組み
診療研究
定期通院糖尿病患者の孤独死の現状とその対策(第4報)
─治療中断と医療費の視点から─
●2008年〜 2015年の間に定期通院していた糖尿病患者(1469人)のうち101人の死亡者がでたが、うち孤独死は8人であった。
●2008 年11月〜12月に受診したインスリン患者340人のうち2014年11月〜12月まで6年継続通院できたものは235人(69%)であり、中断は35 人(年間中断率1.7%)であった。
●2014年インスリン患者1人当たり月間総医療費(伊藤内科クリニック+調剤薬局)は33,810円と治療中断の原因となりうる額であった。
●2008 年11月〜12月に受診したインスリン患者340人のうち2014年11月〜12月まで6年継続通院できたものは235人(69%)であり、中断は35 人(年間中断率1.7%)であった。
●2014年インスリン患者1人当たり月間総医療費(伊藤内科クリニック+調剤薬局)は33,810円と治療中断の原因となりうる額であった。
支台築造とファイバーポスト
第3回(最終回) ファイバーポストとファイバーポストコア
●歯科臨床において、支台築造は機能回復を行うために高い臨床的意義があり、生活歯、根管処置歯を問わず歯冠補綴を行う際、多くのケースで支台築造が行われます。第1回で2016年1月から「ジーシー ファイバーポスト」が保険収載された経緯について、第2回はレジン支台築造の位置づけと支台築造の臨床ガイドラインなどについて解説しました。最終回の今回は、ファイバーポストとファイバーポストコアを取り上げます。
シリーズ
会員
ドクターのつぶやき川柳
詰碁・詰将棋
総目次(2016 年1月号〜12 月号)
編集後記・次号のご案内