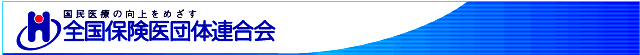1,休保制度の生い立ち
(1)国民の健康を守るために、昼夜を問わず責任を持ち医療に携わっている「開業医」が、傷病によって休業を余儀なくされた場合には、傷病手当ても無く、開業保険医の生活を支えるには決して十分な水準とは言えない「国民健康保険」や「医師国保」に頼るしかありませんでした。
(2)こうした中で、長期に休診・休業せざる得なくなると、患者・家族・スタッフを悲惨な状態にさらすこととなるため、無理を重ねて就労し不幸を招くケースも少なくありませんでした。
(3)神奈川県で、一人の開業医が病に伏し長期休業に追い込まれ、ついには生活保護を受けなければならないような事態が発生しました。この出来事が、会員(開業保険医)の傷害・疾病による休業時の生活安定に寄与することを目的とし、代診医の確保などで地域医療を守る上でも重要な役割を果たす「保険医休業保障共済制度」(以下休保制度)が生まれる契機となりました。
(4)「病気や怪我の場合でも、医院経営や診療活動について心配することなく安心して療養できる方途はないものか」、「自分が療養している間も患者・家族・スタッフを守りたい」などの切実な要求に応えることは困難であり、生保会社や損保会社にも救済できるような商品は皆無でした。保障内容では最も近い商品を扱っていた損保会社でも、掛金設定(加入時のまま固定・低事務費)と自宅療養部分の保障などが難しく、団体商品化が実現しないことがわかりました。
(5)休保制度は、開業医が自ら何らかの制度を開拓しなければ、安心して診療できないということから、6協会と協力いただける生保会社によって検討が進められ、疾病休業給付等を自家共済、傷害休業給付を損保会社に委託(その後自家共済に)、弔慰給付・中途脱退給付を生保会社委託で発足しました。以下の歴史を経過し、開業医・勤務医の医業を支え続けています。