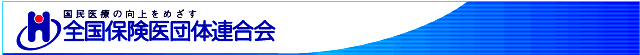日本の公的医療保険が機能しなくなるTPP参加に反対です
2013年6月24日
私たち医師、歯科医師104,000人で構成する全国保険医団体連合会は、日本の国民皆保険制度を守り、発展させることを目的に活動している団体です。
日本の公的医療保険制度は、全国民に公平、平等な医療を保障する国民皆保険システムで、1961年4月に発足し52年目を迎えました。国民の健康達成度はWHOの評価も高く、健康の維持増進に大きく寄与しています。その特徴は、全ての国民が加入対象で、診断・治療・検査・手術・医薬品などの医療が患者に直接提供されます(例外的に現金の支給もあります)。患者は自らの判断で選んだ医療機関を受診できます(フリーアクセス)。その施設数は国内全域に及び、病院8,605施設、医科診療所99,547施設、歯科診療所68,156施設です。医療提供に要した費用は、国庫、保険料から全国共通の公定価格で医療施設に支払われます。公的医療保険がカバーした医療提供の費用は、2011年度で約37兆8000億円(4,740億ドル)※1にのぼります。
TPP交渉では、①医薬品の特許保護の強化として、先発医薬品メーカーが新薬の臨床実験データの独占権を持つこと、②各国政府の医薬品の保険償還価格の決定過程に製薬会社を参加させる、特別な安全性、質、効果を持つ医薬品はプレミアムをつけて高く評価する、などが協議されていると伝えられています。
全国保険医団体連合会、日本政府がそれぞれ調査した「医薬品価格の国際比較」では、いずれも日本よりアメリカは医薬品価格が高い結果となりました(イギリスを100とした価格は、日本が197~222、アメリカは289~352です)。TPPに参加すれば、アメリカの高額な医薬品価格が押し付けられ、日本の公的医療保険の医薬品価格が高騰する可能性があります。日本の公的医療保険がカバーする医薬品の費用は約9.8兆円(1,124億ドル)から約11兆円(1,260億ドル)※2と推計されます。そのことによって保険財政の悪化が懸念され、診断・治療・検査・手術などの医療の費用が削減される危険性があります。
また、先発医薬品メーカーが新薬の臨床実験データの独占権を持つことに対して『国境なき医師団』は、途上国で使われるエイズ治療薬の8割以上が後発医薬品(ジェネリック)であり、これらの医薬品価格を高止まりさせて治療の機会を狭めると指摘し、アメリカの「誤ったビジネスモデル」で「人命が左右される事態になる」と批判しています。
アメリカでは、「診断・治療・外科的方法」が特許保護の対象になっています。TPP参加によって、新しい治療方法や手術などが特許保護の対象となる可能性は否定できません。特許を取っている手術が独占されることや、新たに特許料の支払が必要になることが心配です。日本政府が公的医療保険財政の悪化を回避するため、特許を取った治療方法や手術方法などが、公的医療保険の適用外に固定化されることが懸念されます。
アメリカやシンガポールなどは、営利企業病院があたり前の国です。日本がTPPに参加した場合、日本政府が法律で規定した営利企業病院の参入禁止が非関税障壁とみなされ、撤廃の対象となる可能性があります。営利企業は、出資者に対する剰余金の配当を最優先するため、コスト削減による安心・安全の低下、不採算の部門や地域からの撤退、患者の所得額による選別といったことが懸念されます。日本政府は、「剰余金配当については、非営利性を損なうものであり適当ではない」との見解を公表しています。
TPPに盛り込まれる方向のISD条項は、例えば、日本政府が公的医療保険の適用を前提として臨床研究している「先進医療」を公的医療保険適用に移行する場合、「先進医療」を対象とした保険商品の売上げに影響が出るという理由で、ISD条項を使って国際投資紛争仲裁センターに提訴することが可能となります。保険会社が商品販売のために、公的医療保険への適用自体をやめさせることができるわけです。また、日本政府が公的医療保険の医薬品価格を引き下げようとした場合、製薬メーカーが損害を被るとして、ISD条項を使って提訴することも可能です。
アメリカは、民間医療保険が原則で、保険料の額によって給付範囲が決まります。先進国ですが4800万人以上の人が無保険者で、国民の6人に1人が医療保険に加入できず、まともな医療を受けられない国です。しかも世界で一番医療にお金を使っている国です。日本の公共放送局のテレビ番組は、「危機にひんするアメリカの歯科医療」を放映しました。歯の治療で国民の3人に1人が費用を出せないため治療を断念しているそうです。
日本がTPPに参加すれば、全ての国民が公的医療保険に加入しているという形は保持されても、公平、平等な医療を保障している国民皆保険の機能が失われる危険性が高いのです。
以上の理由から、私たち医師、歯科医師104,000人で構成する全国保険医団体連合会は、TPP参加に反対しています。
私たちはTPPに反対する米国をはじめとする関係諸国の医師・歯科医師と協力し、協議の内容の情報交換と検討を行っています。協力を求めます。
お問い合わせなど :tpp-hdr@doc-net.or.jp
※1 1ドル87.16円 (2010年平均為替レート)※2 1ドル79.807円(2011年平均為替レート)