5章 日本の医療 世界からみると
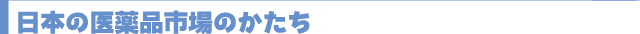
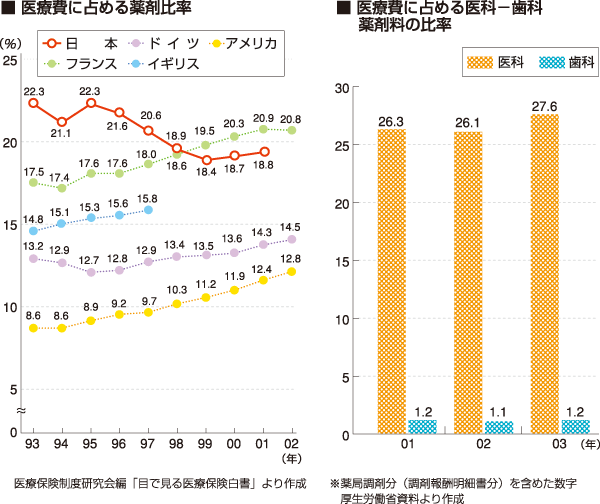
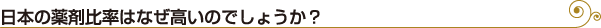
「飲めないくらいたくさんの薬」を医療機関がだすため、医療費が高くなる、という話があります。たしかに、医療費全体に占める薬剤費の割合は、急速に減ってきているものの、約19%と諸外国と比べて高いレベルになっています。調剤薬局の薬剤費を含めると、2003年医科では27.6%になります。
その理由は、薬価(薬の公定価格)が高く設定される新薬の比率が高いからです。
一人の患者さんに処方する薬剤の種類・量は、統計的にみても決して多くありません。厚生労働省が高すぎる新薬の価格を、国際的に適正な額にまで引き下げることで、薬剤比率も、医療費全体も抑えることができます。これについては、経済産業省も「1兆5千億円程度削減できる」との試算を発表しています。
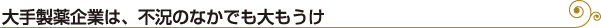
不況下でも大手製薬企業は他の業種と比べ極端に高い収益を上げており、大手15社の平均売上高経常利益率は20.1%となっています。
このような高収益をあげる理由のひとつとして、公定価格の薬価が高いことがあげられます。とりわけ、「新薬」といわれる薬剤は、薬価が高く設定されていますが、そのシェアは大手15社でほぼ100%を占めている状況です。また、90年以降画期的新薬と呼べる新薬が開発されていない中で、製薬メーカーは薬価算定についての評価をより一層強めるよう求めています。
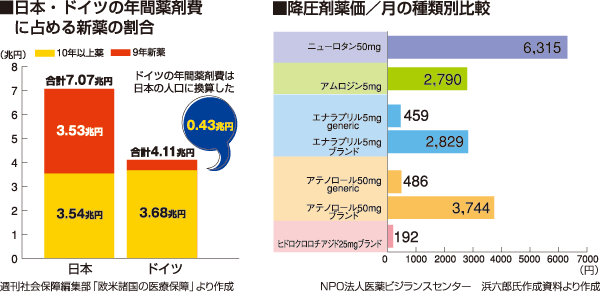
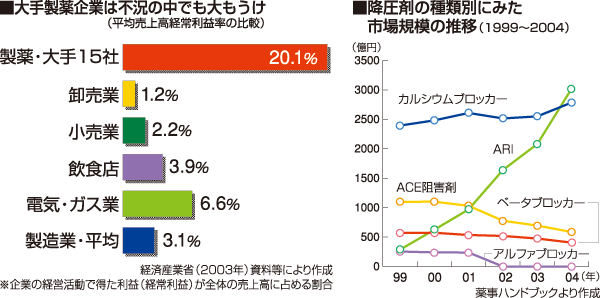
|