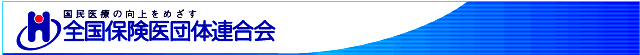高額薬剤「適正使用」へ議論開始
―ガイドラインで医療機関等に要件、患者の「選択基準」―
厚生労働省は7月27日、中医協総会に高額薬剤に係る対応案を示した。単価が高く市場規模が極めて大きいなどの「高額薬剤」について、当面の対応として、最適な使用を推進するためのガイドライン(GL)を策定し、その医療保険給付上の取り扱いを検討する。オプジーボ(抗がん剤)については、2018年改定を待たずに薬価を引き下げることも選択肢に含め対応を検討するとした。
また、薬価制度改革に向けた対応として、改定の谷間での効能追加等による市場拡大に対する対応や、医薬品の特性や既存治療に係る費用との比較等も踏まえた対応等「薬価の在り方全般について抜本的な見直し」を進めていくとした。
具体的な検討は薬価専門部会で進め、オプジーボについては年内に結論を出す。
給付上の取り扱いもGLで検討
厚労省は、新規作用機序を持つ医薬品は、有効性の発現や安全性、副作用の出方などが既存薬と異なるため「最適な使用」の推進が必要として、個別医薬品ごとに、適切に使用できる医師・医療機関等の要件、使用が最適とされる「患者の選択基準」を盛り込んだGLを作成するとしている。
薬事承認に際して、添付文書の承認と並行して、新たにGLが策定される。次いで薬価収載段階で、保険給付上でのGLの取り扱いが議論される。関係学会、PMDA(医薬品医療機器総合機構)が、厚労省の依頼により「科学的根拠」に基づきGLを策定する。GL違反の使用は給付外とするかどうかも検討する。GLが保険給付に関係する場合は、点数表通知等で示される予定だ。
本年度は、オプジーボとレパーサ(高脂血症用薬)について策定する。
効き目・副作用等管理を強調
提案趣旨等からは、GLは、効き目が期待できる患者に限った使用、多大な副作用の恐れがある場合には使用は控える、副作用・緊急時の対応が可能な医療機関、対象疾患等に関して一定の診療経験・専門的知識を持つ医師に使用を限ることなどを盛り込む形になりそうだ。治験データ等を基に有効性・安全性を記した添付文書を受けて、さらに「科学的根拠」に基づいて使用が最適とされる患者や医療機関等が絞り込まれる。
当初、オプジーボ等について、年齢制限等を含めた「総量規制」も求める声が財務省・財政制度等審議会で出され波紋を呼んだ。今回、厚労省は、使用上の安全管理が強く求められる医薬品について、「科学的根拠」に基づいて適正使用を進めて使用を抑制する方針を打ち出した形となる。
患者選定は慎重な議論が必要―医師の裁量、患者の声へ配慮を
GLの記載をめぐり、患者の個別性に応じた医師の裁量権に配慮するよう強調する診療側委員に対し、支払側委員は査定を念頭に定量的基準で限定するよう求めている。
他方、オプジーボのように、効果や副作用が投薬前に予測困難な場合について、最適なケースをどう科学的に選定するかなど技術的課題も指摘されている。
医師・医療機関の要件では、例えばがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院がない2次医療圏が依然84あり、治療へのアクセス確保も配慮が求められる。
重篤な疾病・慢性疾患に優れた薬効や延命効果を示す薬剤がGLの主な対象となることが予想され、患者の選定は倫理・道徳的次元にも関わる議論となる。GLの科学的根拠・策定過程の透明性の担保とともに、患者の声や救済にも十分配慮した策定が求められる。
「最適使用推進ガイドライン」の概要(案)
策定趣旨 |
|
||||
対象医薬品 |
|
||||
内容 |
|
||||
策定の流れ |
|
||||
その他 |
|
中医協総会資料(2016年7月27日)に基づき改変作成
以上