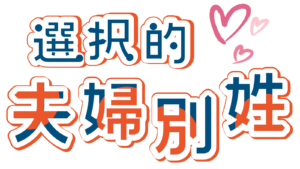第15回 婚姻・離婚の繰り返しで不便を回避したけれど
内山 徹 第3次選択的夫婦別姓訴訟原告
日本の民法750条では、夫婦同姓が義務付けられています。しかし、この規定がさまざまな問題を引き起こしていることをご存じでしょうか?
私たち夫婦の選択
私たちは婚姻に際し、妻の氏が変わることによる不利益を懸念しました。私自身には改姓によるリスクや不利益がほぼありませんでしたが、私の名字が変わることで家族や社会からの視線が気になり、夫婦同姓を受け入れることができず、事実婚を選択しました。
しかし、勤務先の社宅に入居する際、半年以内に婚姻届を提出するよう求められたことがありました。この時、法律婚を選択せざるを得ませんでした。
婚姻・離婚繰り返し
私たちは、婚姻や離婚を繰り返すことで社会制度上の不利益を回避してきました。社宅入居、妻の氏での母子手帳の取得、ペアローンの契約など、婚姻が求められる度に、手続きを行うしかなかったのです。
ある時、私自身が妻の氏を名乗ったことがありました。転職の時期と重なったこともあり、「新しい環境で生まれ変わるつもりで」と前向きに考えていたのですが、何か胸に引っかかるような感覚を覚えました。後になって振り返ると、それは「アイデンティティの喪失」からくるものだったのではないかと思います。さらに、母にそのことを知られ、「なんで…」と涙ながらに責められた時、自分の選択を改めざるを得ませんでした。
夫婦別姓問題と私たちの気づき
私たちのように婚姻と離婚を繰り返すことで不便を回避できたとしても、相続や医療同意といった法律婚でしか得られない保護は得られません。年齢を重ねるにつれ、この問題を無視できなくなりました。
さらに、私は妻の勧めで選択的夫婦別姓訴訟の当事者として参加することになり、他の原告や弁護士の話を聞く中で、この問題が単なる個人の不利益にとどまらないことを理解しました。夫婦同姓の強制は、アイデンティティを奪い、個人の尊厳を傷つけるものであり、特に女性に不利益を強いる構造的な問題があるのです。事実、日本では改姓する配偶者の95%が女性です。この現状は、男女差別意識の温床となっていると言えるでしょう。
選択的夫婦別姓制度がもたらす未来
私たちがこの制度の実現を願うのは、ただ自分たちのためだけではありません。未来の日本で、結婚する若者たちが私たちのような苦労をしなくても済むように、また自分のアイデンティティを守りながら人生を選択できる社会にしていきたいと考えているからです。
(全国保険医新聞2025年1月25日号掲載)
 (うちやま・とおる)
(うちやま・とおる)
第3次選択的夫婦別姓訴訟原告。妻の誘いで原告になったが、本音は誘いを断った時の妻の顔を見るのが怖かったからというのはナイショでお願いします。