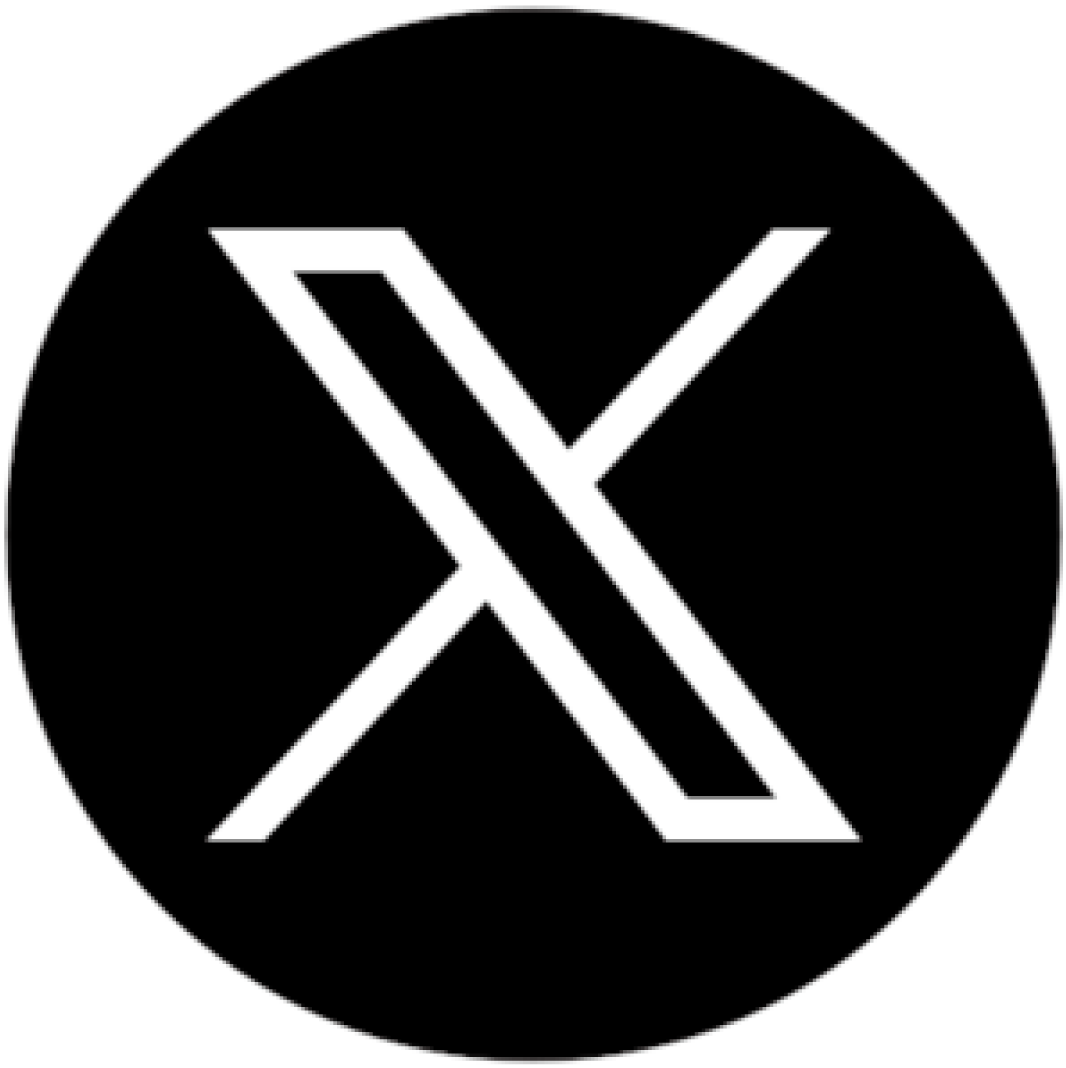|
| 福岡県立大学講師 阪井裕一郎氏 |
| さかい・ゆういちろう 1981年、愛知県生まれ。福岡県立大学人間社会学部専任講師。慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程修了。博士(社会学)。専門は、家族社会学。著書に『仲人の近代』(青弓社、2021年)。 |
女性差別への反対やジェンダー平等を求める運動が盛り上がりを見せる。一方で、「女性の社会進出で晩婚化し少子化の原因になっている」「子どもは母親が育てたほうが良い」など、旧態依然とした意見も根強い。こうした声に対して、「女性の就労が普及した国ほど出生率が高くなる傾向がある」と指摘するのは、福岡県立大学講師の阪井裕一郎氏。ジェンダー平等の実現を阻む「家族主義」を、社会の価値観のアップデートと社会保障充実などで脱却することが重要と強調する――
女性の就労普及するほど出生率上がる
内閣府が2021年3月に公表した「少子化社会に関する国際意識調査」で、「(自分の国が)子供を生み育てやすい国だと思うか」との質問に対し、「とてもそう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した割合は、スウェーデン97.1%、フランス82.0%、ドイツ77.0%であったのに対し、日本は対象4カ国最低の38.3%にとどまった。この背景にあるのが「家族主義」である。これは育児や介護などのケア責任が家族に押し付けられている社会を意味する。
日本の家族主義を象徴する調査結果がある。2012年に各国で実施されたアンケート調査に「就学前の子どもの世話は、主に誰が担うべきか」という質問項目があるが、日本では8割が「家族」と答えたのに対し、北欧諸国では6~8割が「政府や自治体」と回答している(柴田悠『子育て支援と経済成長』)。
戦後の先進諸国は女性就労率の上昇とともに出生率が低下するという共通の歴史をたどった。それゆえ、長らく女性の就労率の上昇が少子化を引き起こしたと考えられてきた。
しかし、現在では女性就労率と出生率に関するこのような通説が誤りであることが国際調査で明らかになっている。OECDのデータでは、女性の就労が普及した国ほど出生率が高くなる傾向が示されている。出生率は、社会全体が男性稼ぎ主社会から男女平等社会に移行する初期段階では低下するものの、男女平等社会が成熟するにつれて上昇すると指摘される。
日本で少子化が進行する一方で、保育園に入れない「待機児童」の増加が問題になるのは、女性の継続的就労を考慮しない社会・制度を作ってきた象徴的な出来事といえよう。
日本や韓国、南欧などの超低出生率国に共通するのは、「家族主義」が強固だということである。福祉社会学者エスピン=アンデルセンは、現代では「伝統的な家族主義」がむしろ家族形成の足かせになっており、福祉の「家族主義」を脱することこそが「家族の絆」を強化するという逆説を示している(『平等と効率の福祉革命』)。
男性もケアの担い手に 制度の後押しも
女性の就労率も出生率も高い国では、家庭と仕事の両立を政策的に推進してきた。一方、日本では、出産・育児期の20代後半から30代後半の女性就労率が低下する「M字型就労」の傾向が根強い。第一子出産を機に6~7割の女性が仕事をやめるという調査結果もある。子育て支援の不足により多くの女性が就業中断を余儀なくされ、女性の能力や経験を社会が有効に活かすことができていない状況にある。
父親の育児関与の度合いが出生率に大きな影響を及ぼすことを多くの研究が実証している。しかし、日本の男性の育児時間は世界的に最低レベルである。総務省「平成28年社会生活基本調査」によれば、6歳未満の子がいる世帯で、1日の家事・育児等の時間は、妻7時間34分に対し、夫は1時間23分。夫が3時間程度を占める欧米諸国と大きな差がある。男性の育休取得率も上昇傾向にはあるが、国際的にみればその水準はきわめて低い。育休を取る男性が否定的にみられる風潮もあり、制度があっても利用されない現状がある。
共働き世帯は年々増加し、2019年時点では専業主婦世帯575万世帯に対し、共働き世帯は1,245万世帯である。しかし、共働き世帯でも男性の家事・育児時間はきわめて短く、子育てが母親ひとりの責任になっている状況は変わらない。社会学者ホックシールドが「セカンド・シフト」(第2の勤務)という言葉で示したように、就業する女性は家庭の内と外の二重の労働を強いられる状況である。
ジェンダー平等が達成されるためには、女性の就労支援だけでなく、「男性がケアの担い手になること」が不可欠である。競争を重視する「男らしさ」の価値観やケア労働そのものの社会的意義が見直される必要もある。
北西欧で大半の男性が育休を取得するようになった契機が「パパ・クオータ制度」の導入であった。1993年にノルウェーで最初に開始された制度で、子ども1人につき育休を最長で59週間取得でき、うち10週間は配偶者が交代して取得することを義務づけるという内容である。導入前には5%に過ぎなかった取得率が90%以上まで向上し、出生率も上昇した。先例によって風穴があき、変化が進む可能性は高い。意図的に「ロールモデル」を作り出すことが意識や行動を変革するうえで効果的であろう。
多様なパートナー関係とケア関係の承認へ
日本のジェンダー平等を阻む要因の1つとして、画一的な家族観もある。つまり、婚姻関係にある異性愛者の男女と血縁関係にある子からなる家族形態のみを「標準」とみなし、その他を「逸脱」や「病理」とみなす家族観である。
「結婚しない人が増えたから少子化が進んだ」という「常識」も疑ってみる必要がある。実は先進国のなかで出生率が高い国でも婚姻率は減少傾向にある。それでも出生率が高い理由は何か。その一つに婚外出生率の上昇があげられる。OECD Family Databaseによれば、2018年時点の婚外出生率は、日本が2%程度であるのに対し、EU平均、OECD平均ともに40%を超えている。多くの国で「結婚している夫婦が子どもを産む」ことが自明ではなくなりつつあり、法律婚にとらわれない多様なパートナー関係とその出生、子育てを承認しサポートする社会において家族形成が促進されていることがわかる。
家族の多様化という点で、最も象徴的な変化は同性婚の法制化であろう。2000年のオランダを皮切りに、現在、世界30以上の国と地域において同性カップルの結婚が異性カップルと全く同等の結婚として認められている。同性パートナー関係による子育ても一般化しており、男女の異性愛カップルのみを家族生活の基盤とするような常識は消滅に向かっている。
日本でも「かたち」にとらわれないケア関係の実態に焦点化した法・政策への転換が求められている。ひとり親や里親等の非血縁親子を含め、多様な家族形成・子育てのあり方を承認し、制度的に保障している国ほど出生率が高い傾向にある。
社会保障充実も不可欠
家族主義の社会というのは、依存できる相手が家族に限定された社会である。われわれは「依存」と「自立」を対立させる見方を再考してみる必要がある。問題は依存それ自体ではなく、依存先が家族だけに限定されていることである。さまざまな境遇にある人の「自立」を可能にするために「依存」先を増やしていくことが重要である。
その際に不可欠なのが、子育て支援策や保育施設の拡充、高齢者の生活を支える介護保険の拡充や、医療へのアクセス確保、最後のセーフティーネットである生活保護利用の柔軟化など、社会保障諸制度の充実だ。既存の家族やジェンダー規範と紐づいてきた様々なケアを国や社会が担うことで、自明視されてきた標準家族の機能や固定観念の見直しにつながる。家族依存を脱した上でこそ、ジェンダー平等や多様なパートナー関係に基づく助け合いやケア関係の可能性も開かれていくはずだ。
現代社会のキーワードの一つが「ダイバーシティ」である。家族やその支援においても多様性を前提とし、後押しできることが重要だ。ひとり親家庭や事実婚、里親家庭、同性パートナー関係、国際結婚など、今日では「標準」の家族モデルを設定することは不可能に近い。にもかかわらず、「標準」家族から離れて生活する人の社会的孤立や貧困が問題となっている。ひとり親家庭の子どもの貧困などは、その象徴だ。
多様性を前提とした社会を形成していくためには社会の価値観のアップデートと、それを後押しできる形での社会保障の充実が求められている。