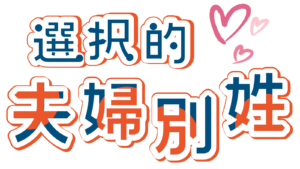第19回 「通称法制化」では解決しない上に問題多く
榊原富士子(弁護士)
1996年以来、2001年、10年、そして今年25年と、別姓導入の気運が高まるたび、「旧姓(通称)の法制化」が対案として浮上してきた。そして今年は初めて野党の維新から法案提出に至った。一方、自民では選択的夫婦別姓に反対する議員らがずっと「通称法制化」を検討していたがまとまらず、法案提出はない。
これまでの個別の「通称拡大」は、確かに婚姻改姓の不利益を一定程度緩和してきた。ただし、それはあくまで選択制導入までの「応急措置」に過ぎなかった。
反対派の「別姓導入阻止ツール」
ここで取り上げる法案としての「通称法制化」は、反対派が意図して使ってきた「別姓導入阻止ツール」である。決して真の解決策ではない。この通称法制化案にはバリエーションがあるが、おおむね「婚姻時に夫婦の氏を選ぶ。婚姻改姓者が旧姓を通称として届け出て、戸籍には旧姓表示欄を新設する。子の氏は夫婦の氏」というものである。
そして、公文書では旧姓使用とし(これには旧姓併記案、旧姓単記案、混在案などがある)、私文書の旧姓使用は努力義務にとどめる。維新案は公文書での戸籍姓使用を認めないが、「使えない戸籍姓」という奇妙な制度は一般の人の理解を得られるだろうか。この通称法制化案の問題を指摘したい。
本名失い混乱続く
一番の問題は、夫婦の一方は自身そのものである本名(戸籍名)を失うことである。
問題2は戸籍姓と旧姓のダブルネームが日常の混乱をもたらし続ける点である。金融機関口座やクレジットカードの旧姓化は非常に難しく、特に海外赴任や出張では偽装を疑われるなど絶えずリスクと隣り合わせである。
問題3は、ダブルネームである限り「戸籍姓(旧姓)」という「併記」をなくすことは難しく(特に住民票は併記しかない)、これがさらに混乱を招く点である。
問題4は、法は(国は)私人や私企業の氏名表記をコントロールできない点である。私企業に努力義務を課しただけで「旧姓単記」が定着するはずはなく、一方、戸籍名があるのに私人に戸籍名使用禁止令など出せない。
膨大な費用と不正の危険
問題5は、膨大なシステム改修費が官民でさらに発生し続ける点である。すでに免許証等の旧姓併記のために少なくとも180億円以上の税金が使われている。今後どれほどの税金が必要なのか誰も試算していないし、日本中の企業経営を逼迫させる要因になる。
問題6は、金融機関の不正防止対応策とダブルネームは相反する点である。また、海外投資は戸籍名のみであり、旧姓の証券会社口座開設は困難と思われる。シンプルな夫婦同姓別姓選択制を望んでいる。
(全国保険医新聞2025年5月25日号掲載)
 (さかきばら・ふじこ)
(さかきばら・ふじこ)
弁護士。第1次・第2次夫婦別姓訴訟弁護団団長。1984年に選択的夫婦別姓をすすめる会を立ち上げた。榊原富士子・寺原真希子編著『夫婦同姓・別姓を選べる社会へ』(恒春閣)ほか。